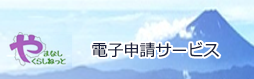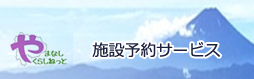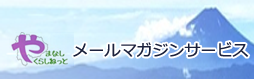市町村職員退職手当の概要
地方自治法第204条の規定に基づき、組合市町村は、条例により常勤の職員に対し退職手当を支給することが定められています。
これに基づき、組合は条例を定め、組合市町村の常勤職員に対する退職手当を支給しています。
市町村職員退職手当の概要
- 支給対象
組合市町村の常勤職員(常勤的非常勤職員を含む。)が退職し、又は死亡した場合に、その者又はその遺族に支給します。なお、懲戒の処分により免職され、又は失職した者等に対しては、原則支給しないこととしております。 - 退職手当の種類
退職手当(一般の退職手当/特別の退職手当)
一般の退職手当:組合市町村の職員が自己都合、死亡、任期満了、定年及び勧奨等の退職事由により退職した場合に支給するものです。
(1) 一般職の退職手当
(2) 特別職の退職手当
特別の退職手当:組合市町村の職員に労働基準法及び雇用保険法による給付に相当する額を特別の退職手当として支給するものです。
(1) 予告を受けない退職者の退職手当
(2) 失業者の退職手当 - 退職手当の支給額
支給額 = 「退職手当の基本額」+「退職手当の調整額」
基本額:退職時の給料月額 × 退職事由や勤続年数に応じ定められた支給率
調整額:職員の区分(役職段階別)に応じ定める調整月額の多いものから60月分の合計額
※定年前早期退職者に対する特例
次の要件を満たす者の退職時の給料月額に対し、その者の満年齢と定年年齢の差1年につき3%(勧奨は2%)を加算するもの
① 定年に達する日から6月前までに退職した者
② 勤続期間が20年以上(勧奨は25年以上)である者
③ 退職日の年齢がその者の定年から15年(勧奨は10年)減じた年齢以上である者 - 勤続期間
(1) 一般職
退職手当の算定の基礎となる勤続期間は、「職員として引き続いた在職期間」において、職員となった 日の属する月から退職した日の属する月までの月単位で計算します(当該期間が1年以上ある場合、11月以下の月数は切捨て)。「職員として引き続いた在職期間」には、組合市町村以外の引き続く国家公務員、地方公務員、相互に通算規定のある地方公社等に出向した職員の出向期間等の在職期間を含みます。
(2) 特別職等
特別職等の職員として在職した月数により計算します(暦法による1月に満たない端数は切捨て)。なお、再選又は再任は通算せず、任期ごとの在職期間により計算します。 - 退職事由
(1) 一般職
自己都合、傷病・死亡(公務上・外)、任期満了、任期終了、定年、応募認定、勧奨等による退職
(2) 特別職
自己都合、傷病・死亡(公務上・外)又は任期満了による退職 - 退職手当の支給制限等
(1) 支給制限処分(全部又は一部を支給しないこととする処分)
① 懲戒免職等処分を受けて退職をしたとき
② 地方公務員法の規定による失職又はこれに準ずる退職をしたとき
③ 退職後、退職手当支払い前に、刑事事件(退職後の起訴の場合は、在職期間中の行為に係る事件)で禁錮以上の刑に処せられたとき
④ 退職後、退職手当支払い前に、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき非違行為をしたと組合市町村の長が認めたとき
(2)支払差止処分(退職手当の支払を一時差し止める処分)
① 職員が起訴され、判決確定前に退職したとき
② 職員が退職後、退職手当支払い前に在職期間中の非違行為について起訴されたとき
③ 職員が退職後、退職手当支払い前に逮捕された場合又は犯罪があると思料するに至った場合で、退職手当を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認められるとき
④ 職員が退職後、退職手当支払い前に、在職期間中の懲戒免職等処分で逮捕された場合又は犯罪があると思料するに至った場合で、退職手当を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認められるとき
(3)返納命令処分(支払後の退職手当の全部又は一部の返納を命ずる処分)
① 退職手当支払後に、在職期間中の行為に係る刑事事件に関し、禁錮以上の刑に処せられたとき
② 退職手当支払後に、在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき非違行為をしたと認めたとき(退職後5年以内限定)
※遺族や相続人から返納を求める場合もあります。
※退職手当の支給制限処分等は、組合において決定します。