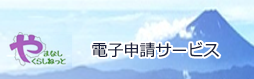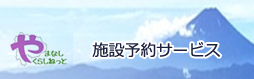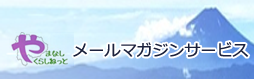経過及び目的
平成13年1月、国が、「わが国が5年以内に世界最先端のIT国家となる」という目標を「e-Japan戦略」で掲げ、これに基づく「e-Japan重点計画」及び「e-Japan重点計画2002」において、平成15年までに電子政府・電子自治体の基盤を構築することとして、諸施策を推進しました。
こうした中で、本県の全ての自治体は、住民の利便性向上と地域産業の活性化と併せ、行政の効率化の実現を目指して、電子行政のあり方を検討する必要が高いという認識から、平成14年度に県及び市町村職員をメンバーとする「電子市町村システム共同化等研究会(事務局:県市町村振興協会)」及び「共同アウトソーシング研究会(事務局:県情報政策課)」において、その対応方策について検討を行いました。
検討の中で、行政手続の電子化に当たっては、システムの構築や運用に多額なコストを要し、また、セキュリティやネットワークに関する高度な知識を有する専任技術者の確保が求められることなどから共同してシステムの開発・運用を行うことが効果的であり、比較的小規模な市町村が多い本県の実情からも共同化の必要性が高いと結論付けました。
また、住民の利便性の向上を図ることはもちろん、行政の透明性やコスト低減を図り、業務プロセスの見直しを含めたさまざまな取り組みを現実のものとするため、民間事業者と公共が、パートナーシップを結び、事業を推進する「包括的アウトソーシング」の枠組みで推進することとなりました。また、契約においては民間事業者と公共が適切にリスクを分担し、安定してサービスの提供を受けるため、SLAに基づく長期契約を締結し、民間事業者の高度なノウハウ等を十分に活用したシステムの構築・運営を行うこととなりました。
そして、こうした検討結果について、県及び各市町村、県市長会、県町村会等の関係各組織での議論を経る中で、「中間組織方式」による県内全自治体の共同化による実現を打ち出し、平成16年4月に住民票の写しの交付請求などの電子申請の受付を開始することとなりました。
具体的な中間組織として、平成15年4月1日に山梨県町村総合事務組合を改組し、7市が新たに加わり県内全域を業務対象とする山梨県市町村総合事務組合(以下「組合」といいます。)において事業を進めていくことになりました。
検討経緯と検討結果(平成14年度)
- 経緯
(1) (財)山梨県市町村振興協会が、「電子市町村システム共同化等研究会」を設置
① 設置:平成14年4月22日
② メンバー:15市町村(県内全市(7市)、郡の代表町村(8町村)、県(市町村課、情報政策課)
③ 市町村における電子自治体システムの共同化のあり方について検討を行い、10月に市町村の共同化は必須であり、県の参加により共同化のメリットが更に発揮される旨の中間報告をおこなった。
(2) (財)地方自治情報センターの共同アウトソーシング調査研究事業を受託
① 期間:平成14年10月~平成15年3月
② 研究会を設置(共同化等研究会のメンバーに合併協職員が参加)
研究会7回、ワーキング会議15回開催 - 共同アウトソーシング調査研究事業の成果
(1) 基本設計について
① 業務の分析を行い対象業務の絞り込み、業務フロー、様式の標準化、シ ステム基本設計、ポータルシステム基本設計などを行った。
② 平成16年度からサービスの提供を開始する業務を絞り込んだ。
市町村:印鑑登録証明書の交付申請、住民票の写しなど効果が高く、実現可能性の高い業務を選択
(2) 共同化の仕組みづくり
① 事業の方向性について次のとおり合意形成した。
・ 県内自治体が共同して電子申請システムの構築・運用を行う。
・ 設計・開発・運用を一括発注するPFIに準じた包括的アウトソーシングとする。
(リスク分担を明確にし、成果に対して支払いを行うこととする)
(債務負担行為に基づく長期継続契約を想定)
② 共同運営形態
・ 共同事業運営組織が参加自治体を取りまとめて、一括してアウトソーシングを行う「中間組織方式」とする。
・ この共同事業運営組織、全市町村が構成員となる市町村総合事務組合とする。
(3) 費用負担について
・ 市町村間の負担割合については、合併などの要素による変動を緩和し、利用数
等便益による公平性を確保するため、均等割:15%、便益割:15%、人口割:70%
とする。
(4) 事務局体制
・ 組合に「電子自治体推進室」を新設